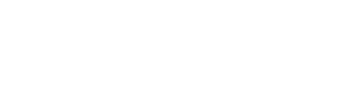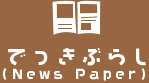136号(2000年07月)8ページ
さらばゴロン

二〇〇〇年七月一六日、私はこの日を永遠に忘れることはないでしょう。ローランドゴリラのゴロン(オス)が、亡くなった日であるからです。
ゴロンの死亡を確認し獣舎の外へ出ると、その日は折しも百年ぶりの皆既月食を迎えていました。正に月が見えなくなる寸前で、ゴロンの死に合わせたかのようでありました。 私も飼育係を三十年余り経験してきて、担当、代番動物を含め数多く動物たちを見送ってきましたが、正直今回ほどの喪失感を味わったことはありません。こんな思いは、肉親との別れにも似た感情といえるかもしれません。
十数年の彼との付き合いでしたが、その半分近くは彼との信頼関係を築くのに費やされたと言っても過言ではありません。世話をすることになっての初めの頃は、飲み物、食べ物を与えようとしても全く近寄ってくる気配さえ見せませんでした。
いたずらに時間だけが過ぎ、担当者が見かねて傍にきて呼ぶと、直ぐにきて食べ始める毎日でした。無力感で泣きたくなるほどでしたが、それでも誠意が通じてか徐々に心を開いてくれるようになりました。
ある日、放飼場の片隅に石ころがあったので、彼にもってきてもらおうと黙ってその石を指差しました。すると、なんと彼はすぐに石を取りにゆき、私のところへ来て、オリの間から差し出しました。今までの苦労が消し飛び、涙が出るほど嬉しくもありました。
ここまでくるのに、六年近くも年月が経過していました。それからは私も精神的にリラックスした状態で彼に接しられ、毎日を楽しく過ごせるようになりました。
代番作業の中での思い出は、調理室で餌作りをしている時、何か気配を感じて振り向くと、覗き窓から彼が大きな顔を覗かせていて「なんだ、何か食べたいのか」と声を掛けると、のどを鳴らして返事をします。餌の一切れを口の中に入れてやると、満足そうに窓から顔が消え、又餌作りに勤めました。
ゴロンがいなくなっても、餌作りの仕事は変わりません。が、なぜかその最中に度々振り向いて覗き窓の方を見ている自分がいます。このこと一つを見ても、私の心の中に占めていた彼の大きさを感じずにはいられません。(合掌)
(池ヶ谷 正志)